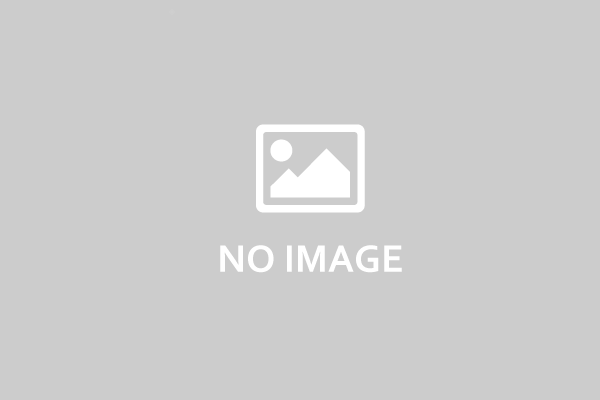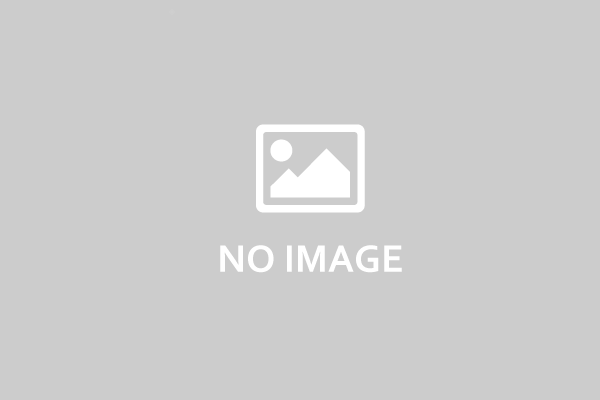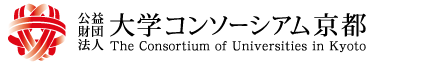産学連携教育プログラム 実習先検索:結果詳細
結果詳細は以下のとおりです。
実習先基本情報
| 実習先ID | 3487 | コース | プロジェクト企画実践 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実習先名 | 一般社団法人 京都ソーシャルビジネス・ネットワーク (Kyoto-SBN) | 実習先名カナ | キョウト ソーシャルビジネスネットワーク | ||||||||||
| 業 種 |
|
||||||||||||
| 所在地 | 〒612-8088 京都府京都市伏見区桃山町金森出雲28 |
||||||||||||
| 写真(社内の様子) | |||||||||||||
| 企業サイト | https://kyoto-sbn.org/ | ||||||||||||
| その他サイト |
https://www.youtube.com/@wakuwaku-fushimi
※youtubeチャンネル
https://lin.ee/zXnMRNw
※LINE公式アカウント
https://www.facebook.com/koyama9705/
※Facebook(代表個人)
|
||||||||||||
| 事業内容 | 小中学生を主な対象に、「地域・社会に貢献する人材」を育成する教育プログラムを企画・運営する法人です 探求学習、課題解決型学習、キャリア教育などの要素を盛り込んだ体験を通じて、子供たちが、 (1)課題を見いだし解決する力 (2)新たなモノを創り出す力 (3)常識を疑う発想力 を身に付け、予測できない未来を生き抜く人材を育成します |
||||||||||||
| プログラム実施の 目的 |
子ども、実習生、当法人それぞれにメリットがあるため (1) 子ども→5~10年後の自分の姿を想像し、将来自分たちが身に付けていく力とは何かをイメージしやすくする (2) 実習生→もっとも学習定着率の高い学習方法は「ほかの人に教える」ことである(アメリカ国立訓練研究所のラーニングピラミッド)、VUCAの時代を生き抜く力とは何かを子供たちに教えることは自分自身の成長にもつながる (3) 当法人→学習プログラムのレベルアップ。Z世代の中間世代(18~22歳)、最終世代(10~15歳)それぞれから、彼らにフィットする学びのスタイルのフィードバックを得ることにより、さらなる学習プログラムの向上につなげる |
||||||||||||
| 選考方法 | 2次選考あり(出願・面接後、受入れ先が指定する選考方法により決定) | ||||||||||||
| 2次選考の詳細 | 受入れ先が面接を実施します。 | ||||||||||||
| 面接内容 |
|
||||||||||||
| 選考に関する備考欄 | |||||||||||||
実習部署情報
| 実習部署又はプロジェクト名 | 未来を生き抜くチカラを子供たちに!~子供たちの成長をサポートし、自らも成長する~ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施方法(予定) | 対面とオンラインを併用して実施する | ||||||||||
| 実習地住所 | 京都府 特に決まったオフィスは構えていません。 リモートワーク的な働き方(Zoom、Canva、OneDrive、ペライチなどを使っています)も積極的に体験してもらいながら、必要に応じてリアルなミーティングを利便性の良い場所(四条烏丸や京都駅界隈)で実施します また、学習プログラム実施場所の下見なども行います | 実習地の最寄り駅 | 四条烏丸や京都駅界隈(予定) | ||||||||
| 選考方法 | 2次選考あり(出願・面接後、受入れ先が指定する選考方法により決定) | ||||||||||
| 実習内容 | 当法人では、2025年に全部で6つの事業に取り組むことを計画しています 詳しくは、こちらのWEBサイトで! https://kyoto-sbn.org/volunteer 「2025年度の事業計画はこちらから」バナーをクリックすると、PDFファイルが開きます この表にある6つの事業を大きく分けると、次の3タイプになります A すでに、実施プログラムの大枠がほぼ固まっているもの (WEB1ページ目の表の(1)、(2)) B 公的機関から資金面での支援を受けるための申請中またはこれから申請段階にあり、その結果に応じて実施計画の見直しや詳細設計をしていくもの(WEB1ページ目の表の(3)、(5)) C 事業の構想段階にあり、情報収集や折衝などを通じて、事業スキームをこれから考えていくもの(WEB1ページ目の表の(4)、(6)) 活動期間中(6~10月)に、どのタイプのプロジェクトも動いていますので、皆さんが興味を持ったり、取り組んでみたいタイプの事業に関わってもらうことができます(複数でも可能) Aタイプは、プログラムの実施当日に向けて、告知・広報、役割分担、当日の進行などを考えるオペレーション的な仕事 Bタイプは、申請が採択されるかどうかにより、実施スキームや内容を修正していく必要があり、状況の変化に対応して柔軟な対応が求められる仕事 Cタイプは、当法人のミッションの範囲内で、事業の構想を練り、収支計画を立て、スケジュールを組み立てる仕事 が体験できます ※ 会社に例えれば、Aは事業部門、Bは企画部門、Cは戦略部門のお仕事を体験できます ●活動月予定 詳細は参加いただける学生さんの予定も踏まえながら固めていきます(8月~9月にかけてが業務のピークとなる見込みです) ●活動日・時間 特に固定した活動日や時間はありません 日程調整ツールや、オンラインミーティングなどを活用しながら、できるだけ学生さんにとっても参加しやすいよう調整します **月間活動予定** ◆6月 課題把握・目標設定・活動スケジュール設定 各人がこのコースを通じて実践したいこと、身につけたいことなどを踏まえ、役割分担などを決定します (※参加されるそれぞれの学生さんが体験したいことを考慮します) ◆7月 プロジェクトの開始 役割分担に応じて、上記A、B、C それぞれのタイプのプロジェクトに参加してもらいます(複数参加可能) ◆8月・9月 プロジェクトの実行~完成 主に企画したプロジェクトを実践する期間となります ◆10月 プロジェクトの振り返り・プロジェクト・プレゼンテーションに向けた準備 ここまでの取り組みを、様々なステークホルダーとも意見交換しながら振り返り、可能であれば今後のプロジェクトの提案なども行ってもらいます (※参加されるそれぞれの学生さんの振り返りや発表のサポートにも配慮します) |
||||||||||
| 実習のアピールポイント |
|
||||||||||
| ご担当者様から 学生へのメッセージ |
少子高齢化、地方の衰退、気候変動、AIロボットの進化による働き方の激変 今の小中学生は、一体何がこの先起こるのか誰もが予想できない時代を生き抜いていかなければなりません そのためには、みなさんが小中学生の頃あまり身につける機会がなかった ① 課題を見出し解決するチカラ ② 何かと何かを組み合わせ、新しいものを創り出すチカラ ③ これまでの常識を疑い、必要であれば新しいルールを創り出すチカラが大切です 当法人は、そんな学習を体験型で子どもたちに提供しています でもこうしたチカラは、まもなく社会に巣立っていく皆さん大学生にも必要なのではないでしょうか? 「人から教えられたこと」よりも「人に教えたこと」のほうが、自分の身になり、応用が効きます ぜひ、みなさんも当法人のプログラムに関わってもらい、子どもたちのチカラを伸ばしながら、自分自身も成長してみませんか! |
||||||||||
| 受入予定期間 |
|
||||||||||
| 実働予定日数 | 活動状況による | ||||||||||
| 受入人数 | 2名 ~6名 | ||||||||||
| 学部系統指定 | 指定しない | ||||||||||
| 受入条件・資格 | |||||||||||

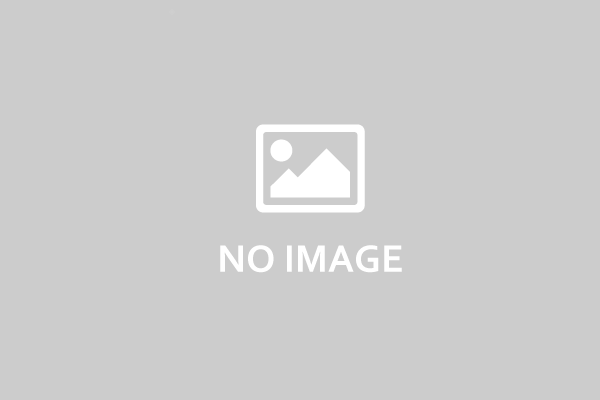
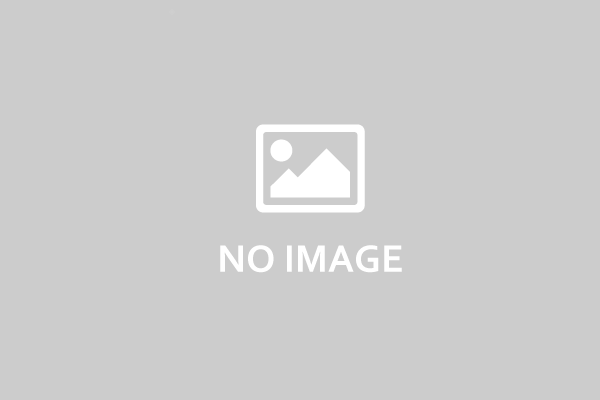
実習先基本情報
|
一般社団法人 京都ソーシャルビジネス・ネットワーク (Kyoto-SBN)
キョウト ソーシャルビジネスネットワーク
|
実習部署情報
|
未来を生き抜くチカラを子供たちに!~子供たちの成長をサポートし、自らも成長する~
|